
ネットネット株とは、バリュー投資の祖「ベンジャミン・グレアム」が提唱した下記の投資基準である。(ネットとは“正味の”という意味。)
( 流動資産 – 負債総額 ) × 2/3 ≧ 時価総額
( 流動資産 – 負債総額 )は「解散価値」と呼ばれる。
もしその企業が事業を継続できず解散した場合に残る資産だ。
まず諸々の資産を売却し負債を返済し、その後に残った資産を株主に分配する。
資産の分配は債権者が先で株主は後となるため、解散価値は別名「株主資産」とも呼ばれる。
係数2/3はグレアムの主観だと思うが、要するに解散価値よりも時価総額がかなり小さければその株は割安と考えるのがネットネット株評価の思想だ。
ちなみに固定資産はソフトウェアや営業権など事業継続を前提に評価されているため、実際に売却する際には二束三文で売り払われる。
このことから、グレアムは固定資産を資産とみなさなかった。
「稼ぐ人の株投資 億超えの方程式2」ではさらに流動資産の中でも換金性の高い資産に絞って評価していた。
商品在庫や仕掛品などは資産から除くという。
逆に固定資産の中でも、換金性の高い投資有価証券は資産に組み込んでいた。
なぜ投資有価証券が固定資産なのかという疑問が湧く。
会計基準上の区分としては1年以内に現金化する予定のないものが投資有価証券で固定資産、1年以内に現金化する予定があるものが有価証券で流動資産となる。
投資有価証券を1年以内に現金に換えたからといって罰則があるわけではない。
違いは、現金化した場合、投資有価証券は特別損益、有価証券は営業外損益となること。
したがって、確かに投資有価証券を資産に組み込むことは合理性がある。
四季報でどこまでできるかは確認できていないが、まずは簡便なグレアムの基準から進めていこう。



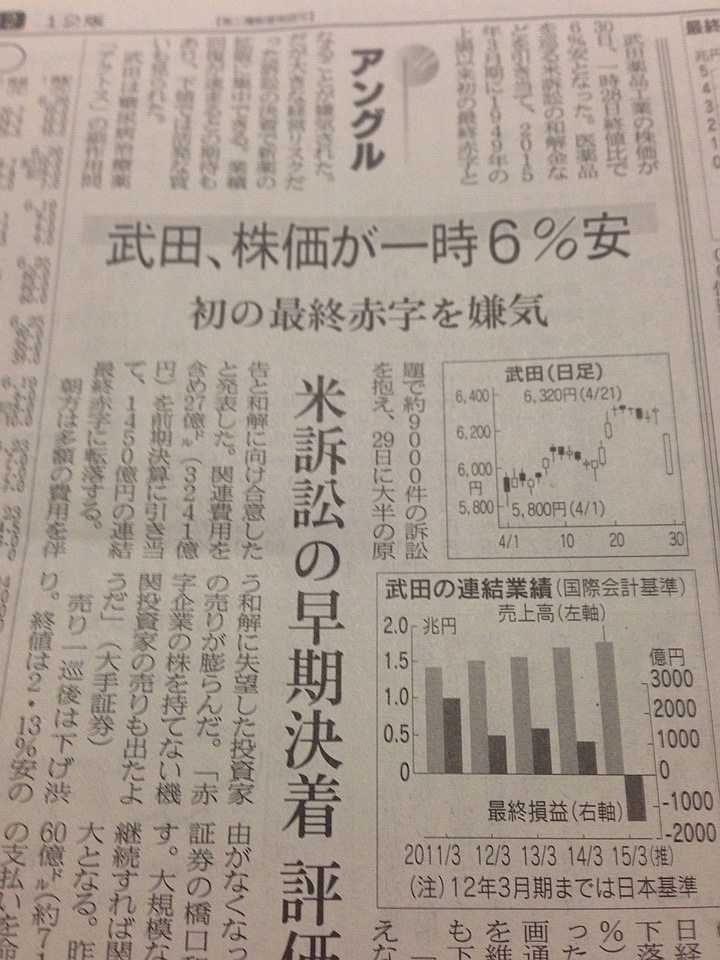


こんにちは。ネット・ネット株について調べていたら,ここに流れつきました。
株の初心者なので,いろいろ教えて下さい。
> ( 流動資産 – 負債総額 )は「解散価値」と呼ばれる。
解散価値=清算価値=流動資産-流動負債ではないのでしょうか。
> もしその企業が事業を継続できず解散した場合に残る資産だ。
ここでいう,「資産」とは,何を指しているのでしょうか。
解散したら,清算手続に入りますが(会社法475条1号),この場合,原則として全ての資産が換価(=清算)の対象となります。
> 資産の分配は債権者が先で株主は後となるため、解散価値は別名「株主資産」とも呼ばれる。
「株主資産」という言葉は知りませんでした。「株主資産」について記述している書籍を教えて下さい。
> このことから、グレアムは固定資産を資産とみなさなかった。
賢明なる投資家「財務諸表編」(ベンジャミン・グレアム & スペンサー・B・メレディス)では,
「有形固定資産勘定を額面どおりに受け取ってはならないが、かといってそれを完全に無視するのも間違っている。」
と記載されています。
ここでいう,「固定資産を資産とみなさなかった」のは,「無形固定資産を資産とみなさなかった」ということでしょうか。
よろしくお願します。
ベンさん
はじめまして、渾身です。
勉強熱心な方で、感心しました。
自分も財務諸表の読み方を勉強しながら書いていたので、記述が甘い部分があります。
逆にいろいろ教えていただければと思いますが、再度調べた範囲でお答えしますね。
>解散価値=清算価値=流動資産-流動負債ではないのでしょうか。
こちらは固定負債の取り扱いですよね。
ネット上の記述だと、解散価値=流動資産-総負債の方が多かったのでこのように書きました。
たとえば下記。
http://www.geocities.jp/y_infty/graham/gr_09.html
下記を見ると、固定負債とは退職金引当金や繰り延べ税金負債なので、道義的な意味でも株主よりも先に支払われるのでしょうか?
http://www.geocities.jp/lennox1225/kantan1.html
また下記を見ると、グレアムは解散価値ではなく、正味流動資産(正味運転資本)で見ているようですね。
http://trendsline.info/value/value.html
そういった意味では、ネットネット株のスクリーニングにおいては確かにベンさんの指摘が正しいと思います。
>ここでいう,「資産」とは,何を指しているのでしょうか。
解散価値の意味で記述しています。
>「株主資産」という言葉は知りませんでした。「株主資産」について記述している書籍を教えて下さい。
すいません、書籍は存じません。
記述していた時期に参照していたサイトに書かれてあったので用いましたが、今はそのサイトはないようです。
株主資産でググってもほとんど出てこないので、あまり一般的な言葉ではないようですね。
>ここでいう,「固定資産を資産とみなさなかった」のは,「無形固定資産を資産とみなさなかった」ということでしょうか。
有形固定資産も含んでいます。
正味流動資産(正味運転資本)の定義としては省かれてあったので。
http://trendsline.info/value/value.html
では、何か他に不備があればコメントください!
こんにちは。丁寧に答えていただいて,ありがとうございます。
> ネット上の記述だと、解散価値=流動資産-総負債の方が多かったのでこのように書きました。
> たとえば下記。
> http://www.geocities.jp/y_infty/graham/gr_09.html
確かに,書いていますね。
ただし,「解散価値 ≒ 流動資産 – 総負債」と書いてあり,その導出過程が記載されているのですね。
一般的には,
「株主資本 = 資本 – 負債」なのですが,
それが,実体を表していないために,いろいろ考えて,「(株主資本 ≒)解散価値 ≒ 流動資産 – 総負債」とみなしたのでしょうね。
この場合,事業の内容や資本構成によって,かなり解散価値の精度にバラツキが出るのではないでしょうか。
この点,「流動資産価値は清算価値をはかる『おおまかな』目安になる」(ベンジャミン・グレアム=デビッド・L・ドッド。証券分析・1934年版,第43章「流動資産価額の重要性」から。『』は私が付けました。)とあるのですが,あくまで,『おおまかな』目安であり,実際に投資をする際には,さらに詳細な分析をしなければならないのではないでしょうか。
賢明なる投資家「財務諸表編」第24章「清算価値と正味流動資産価値」では,さらに,つっこんだ記載があります(同書の初版は1937年)。すなわち,「製造会社について、その清算価値は資産の性質や資本構成などによって注目すべき数字になることもあるし、そうでない場合もある。もし流動資産が相対的に総資産のかなりの部分を占め、負債が一般の企業よりも比較的少ない企業については特に注目する必要がある。」とあり,製造会社においては,清算価値は,目安であって,少なくとも,固定資産比率や負債比率を調べてからでないと,投資案件にはならない旨,書かれているのではないでしょうか。
ちなみに,証券分析の第43章「流動資産価額の重要性」で,流動資産価額を求めるモデルケースに選ばれたのは,トラックメーカーであるホワイト・モータース社,すなわち,製造会社の事例でした
同社のバランスシートでは,「正味流動資産 = 流動資産合計 – 流動負債」とあります。前掲URLのサイトのgraham さんが読んでいるのは,『証券分析【1934年版】』 なので,
http://www.geocities.jp/y_infty/graham/
そこら辺,ちょっと,疑問符が付きますね。
ちょっと,長くなりました。また,時間をおいてポストしますね。長文,お読み下さり,ありがとうございました。
ベンさん
こんにちは、渾身です。
すごい解説、勉強になります!
>もし流動資産が相対的に総資産のかなりの部分を占め、負債が一般の企業よりも比較的少ない企業については特に注目する必要がある。
この記述で思うのは、1企業だけで清算価値を測るのはなかなか難しいのかなと。
利益を上げることを最優先に考えるならば、同一セクターの類似企業間で、できるだけ清算価値以外の要因を除去し、相対的な差異を見いだしてリターンリバーサル(割高を売り、割安を買う)戦略を組むのがよいように思います。
システムトレードの世界でも、このような思想に基づいたトレードはそれなりに市民権を得ていますので。
あとは、マーケットに影響力のある主体がいかなるモデルを使用しているかが重要でしょうね。
たとえば機関投資家の間で最も普及しているBARRAモデルに組み込まれているのであれば、利益を得る上ではそれが正解になると思います。
個人ではなかなかその中身を知ることは難しいのですが・・・。
では、ベンさんのまたのコメント楽しみにしています!
こんばんは。まだまだ,書くことがいっぱいありますね。2014/07/30 20:46 にいただいたコメントは,その後でということで。
> 下記を見ると、固定負債とは退職金引当金や繰り延べ税金負債なので、道義的な意味でも株主よりも先に支払われるのでしょうか?
> http://www.geocities.jp/lennox1225/kantan1.html
負債は,流動負債と固定負債に分かれ,営業循環基準または1年基準の適用があるものは流動負債として扱われ,それ以外のものは固定負債として扱われるものだと,単純に考えていたのですが,どうなんでしょうか。
退職金給付引当金は給料の後払いである退職金の引当金の性格を有し,また,繰延税金負債は正に租税の引当てなので,法律上,一般債権に優先するんだと思うのですが(退職金給付引当金については民法308条,繰延税金負債については国税徴収法8条等)…。退職金給付引当金は道義上も払ってあげた方がいいと思いますが,租税は,どうなんでしょうね。私ならば,法律上,払わなくてもいいのであれば払わないかな…。
繰延税金負債は,営業循環基準または1年基準の関係で,流動負債になる時もあるんだと思っていたのですが,どうなんでしょうね。
さらに,「清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。」(会社法502条本文)ので,当然そうなるものだと思っていました。債務を支払うのは,一般債権者に対する清算株式会社の責任であり,株主(会社の一員)は,清算株式会社の責任を全うした後,自分の持分(株主持分)の分け前をもらうことになるのだと思っていたからです。
それでは,また,時間をおいてポストしますね。長文,お読み下さり,ありがとうございました。
ベンさん
こんにちは、渾身です。
>営業循環基準または1年基準の適用があるものは流動負債として扱われ,それ以外のものは固定負債として扱われるものだと,単純に考えていたのですが,どうなんでしょうか。
自分もこの定義でよいと思います。
投資は美人投票ですから、奇抜なアイデアではなく一般の定義をしっかり負に落とすことが重要かと。
こんばんは。なかなか筆が進まなくて,こんな時間になってしまいました。
「解散価値 = 流動資産 – 負債総額」の根拠とされる,サイト「株道!極め道!!」
http://www.geocities.jp/lennox1225/kantan1.html
なのですが,失礼ながら,サイト主さんの会計に関する認識の誤りが,いくつか見受けられます。
> 1.貸借対照表の読み方
> 貸借対照表は左側に貸方、右側に借方を表し、左側の貸方が資産となります。
簿記や会計の本を読めばわかるのですが,バランスシート(貸借対照表)の左側に記載されるのは借方,右側に記載されるのは貸方です。
そして,借方に記載されるのが,資産です。
> 2.解散価値の算出方法
> 株式の指標でも有るPBRの値は、貸借対照表の左側の資産全てを考慮しておりますが、アメリカで証券分析の父と呼ばれたベンジャミン・グレアムは、(詳しくはこちら)それとはことなるもっと実質的な解散価値の算出方法を編み出したのです。
この記載では,「PBR = (形式的な)解散価値」であるようにも読めると思うのですが,本当は,「PBR = 株価純資産倍率」です。PBR は,Price / Book Value Ratio の略で,PER と同じく,指標に過ぎません。
価値と指標は,比べるものではなく,PBR の場合は,価値は指標を求める際の数値に過ぎません。
解散価値と比べるならば,この文脈からは,Book Value すなわち,簿価になるのかもしれませんが,むしろ,簿価は解散価値を求める際の手掛かりとなると思うのですが…
> グレアムは左側の全てを資産とみなすことはできないと考えたのです。
> とくに固定資産(会社の社屋や会社の所有物)はすぐには現金化しづらく、
> 試算どおりの値段で現金化されるか不明だからです。
> グレアムは固定資産はほぼ資産に値しないと考え、この資産を0と考えているのです。
証券分析の第43章「流動資産価額の重要性」に記載されている,ホワイト・モータース社のバランスシートでは,固定資産の清算価値は,簿価に対して二掛けで計上されています。
以上のとおり,会計に関する認識の誤りが見受けられるので,「解散価値 = 流動資産 – 負債総額」の根拠には,なりにくいのかなと思っているのですが,どうでしょう。
2つのサイトが参考にしているのは,どうやら,「証券分析」のようなので,その解釈が重要なのかなと思います。
それでは,また,残りは明日以降,ポストしますね。長文,お読み下さり,ありがとうございました。
ベンさん
こんにちは、渾身です。
自分も今フリーランスで青色申告を初めてやるのですが、貸方、借方は本当にこんがらがります。
もうあきらめて、税理士に言われたとおり、やよいに入力しています(笑)。
>価値と指標は,比べるものではなく,PBR の場合は,価値は指標を求める際の数値に過ぎません。
これはその通りだと思います。
事業規模や事業内容の異なる企業同士を比較するのには実数より指標を使った方が横比較がやりやすいので、PBRはよく使われますね。
PERよりも経年変化が小さいので使いやすい特性もあります。
少しこんがらがってきたのですが、今までの話を整理すると、
解散価値=流動資産+固定資産×0.2-総負債?
ベンさんの下記記述から推察するに、固定負債は株主に返ってくる性質のものではないので引くべきと解釈したのですが?
>退職金給付引当金は給料の後払いである退職金の引当金の性格を有し,また,繰延税金負債は正に租税の引当てなので,法律上,一般債権に優先するんだと思うのですが
認識の違いがあればご指摘ください。
では!
こんにちは。コメントをいただきありがとうございます。
続きを書くことで,間接的にリプライになるところもあると思うのですが,直接的な返信は書き終わってからということで。
> また下記を見ると、グレアムは解散価値ではなく、正味流動資産(正味運転資本)で見ているようですね。
> http://trendsline.info/value/value.html
むしろ,グレアム師は,株式価値を考えるに際して,「解散価値 = 清算価値」のことを最も重要視していたんだと思います。
賢明なる投資家「財務諸表編」第24章「清算価値と正味流動資産価値」では,
『製造会社の証券の「正味流動資産価値」は清算価値の大ざっぱな数字となる可能性もある。その数字を出すには、…正味流動資産…を算出』するとあるので。難しいけど,なんとか清算価値(=解散価値)を正確に出したいんだという思いが,私には伝わって来ます。
ちなみに,同書の第3部「財務用語の解説」では,正味流動資産のことを「流動資産から流動負債を差し引いたもの。」と記載しています。
上記と関連しますが,サイト「株50円ショップ」でも紹介されている,「正味流動資産(正味運転資本)=流動資産-流動負債」という式を,私も使っています。その後,詳細な分析をしますが。
問題は,
> グレアムの割安株の株価表示は次式で示されます。
> 株価=(流動資産-流動負債)×2÷3÷発行済み株式数
> この時価株価が、上記株価以下であれば割安と判断するというものです。
>> この条件を満たす銘柄をネット・ネット・銘柄とバリュー投資では呼んでいます。
この最後の一文が,正しいのかどうかですね。実は,「株50円ショップ」のサイト主さんには申し訳ないのですが,正しくはないのだと思っています。
ネット・ネット銘柄ではなく,単に正味流動資産価値と時価総額を比較して前者が後者を大きく上回る(1.5倍以上)銘柄,すなわち割安株だと。
あえて,ネットという言葉を使うならば,「正味流動資産 = Net Current Assets」からとって,ネット銘柄とでも言うべきなのかもしれません。
その理由については,この書き込みでは,あえて触れないでおきます。ただ,そう考えるヒントだけ書いておきます。
> http://trendsline.info/value/value.html
サイトでは,ベンジャミン・グレアム著にかかる書籍「賢明なる投資家」が宣伝されています。
同書の第15章「積極的投資家の株式銘柄選択」の,ある一節「グレアム・ニューマン社が行った売買方式の概要」において,「正味流動資産(割安)株」として、
「この売買法の基本は、正味流動資産のみを考えた(つまり、工場設備を含むその他の資産は考慮に入れない)」簿価よりも安い価格で買える株をなるべく多く取得することである。われわれが買い付けた銘柄のほとんどは、この「スリム化された」資産価値の、三分の二以下の価格で入手したものである。この方法ではほぼ毎年、幅広い分散投資(一〇〇銘柄以上)を行っていた。」
とあるものの,「割安株投資 = ネット・ネット株投資」とは書いていません。
また,ジョン・トレイン「マネーマスター列伝」の7章「ベンジャミン・グレアム」でも,同様の基準でした投資法が紹介されているものの,「割安株投資 = ネット・ネット株投資」とは書いていません。
また,長くなりましたが,次は時間をおかずにポストしますね。長文,お読み下さり,ありがとうございました。
こんにちは。
> そういった意味では、ネットネット株のスクリーニングにおいては確かにベンさんの指摘が正しいと思います。
私は,ネット・ネット株は,
「流動資産 – 負債総額」と時価総額を比較して前者が後者を大きく上回る(1.5倍以上)株のことを言うのだと思っています。
ブルース・グリーンウォルド他3名の共著にかかる「バリュー投資入門」では,ネット・ネット株のことを,
『「流動資産マイナス負債総額」の額を大幅に下回る時価の株式』
と定義しているのですが,上記の記載の方が,すっと頭に入るので。さらに言うと,ネット・ネット「株」というのも変だなと思っています。単に,ネット・ネット投資法でいいのではないのかと。
>> ここでいう,「資産」とは,何を指しているのでしょうか。
> 解散価値の意味で記述しています。
ようやくここまで来ました。「解散価値 = 清算価値」の前提で話を進めますね。
証券分析の解釈なのですが,
本来,清算価値は,実際に清算手続で換価してみないとわからないところ,資産の簿価に適当に乗数を掛けて資産価値を出し,そこから負債総額を控除して求めたが,その数字は,「流動資産 – 流動負債( = 正味流動資産価値)」と余り変わらない。そこで,解散価値 = 清算価値 ≒ 正味流動資産価値( = 流動資産 – 流動負債) として分析してみてはどうか。
というのが,グレアム=ドッドの主張なのではないでしょうか。
ここで気を付けておかなければいけない点は,
清算価値 = 清算時流動資産 + 清算時固定資産 – 流動負債 – 固定負債 ≒ 流動資産 – 流動負債( = 正味流動資産価値)
なのであって,固定資産 = 0 ではないということです。
ちなみに,証券分析の第43章「流動資産価額の重要性」では,ホワイト・モータース社のバランスシートを使って清算価値の概算を求めています。
清算価値が,20,300,000ドルであるところ,正味流動資産価値は,22,108,000でした。
それに対して,時価総額は,5,200,000円だったので,これは買いだろうといいたいのでしょう。
次は,時間をおいてポストしますね。長文,お読み下さり,ありがとうございました。
間違いがみつかったので,
> 清算価値が,20,300,000ドルであるところ,正味流動資産価値は,22,108,000でした。
> それに対して,時価総額は,5,200,000円だったので,これは買いだろうといいたいのでしょう。
を次のとおり直して読んで下さい。
清算価値が,20,300,000ドルであるところ,正味流動資産価値は,22,108,000ドルでした。
それに対して,時価総額は,5,200,000ドルだったので,これは買いだろうといいたいのでしょう。
これは,渾身さんの,2014/07/31 10:21にポストされたコメントに対するリプライです。
こんばんは。ようやく,リプライできるようになりました。
> 少しこんがらがってきたのですが、今までの話を整理すると、
> 解散価値=流動資産+固定資産×0.2-総負債?
すでに書いたとおり,
解散価値( = 清算価値) ≒ 正味流動資産価値( = 流動資産 – 流動負債)
だと思います。
> ベンさんの下記記述から推察するに、固定負債は株主に返ってくる性質のものではないので引くべきと解釈したのですが?
>>退職金給付引当金は給料の後払いである退職金の引当金の性格を有し,また,繰延税金負債は正に租税の引当てなので,法律上,一般債権に優先するんだと思うのですが
「固定負債は株主に返ってくる性質のものではない」のはそのとおりなのですが,一般的には,株式の価値を求めるのに,資産から(固定)負債を控除するのは,解釈の問題ではなく,むしろ,当然のことだと思うのですが…
バランスシートの構造を見ると
借方(資産) = 貸方(負債+株主資本)
ですから。
話は変わりますが,このエントリーの題名を見ると「バリュー投資に触れる:ネットネット株を四季報CD-ROMでスクリーニング(2)」なので,スクリーニングの条件式を考えることを目的としていたのでしょうか。
もし,そうならば,四季報CD-ROMで
「スクリーニング」→「株式投資に役立つスクリーニング(上級)」→「連結・時価総額が『流動資産-負債+投資その他資産』の3分の2以下の会社(DL後)」
が参考になるかもしれません。
この条件式は,
http://plaza.rakuten.co.jp/matseto/diary/201110240000/
にあるとおり,バリュー投資界の古参投資家,しんさんが作られたものです。
私は,このスクリーニングと,正味流動資産価値を使ったスクリーニングを,資産のバリューに着目した投資の第一歩として使っています。当然,スクリーニングの後は,詳細な分析は欠かせませんが。
これで,私がこのエントリーで話したいことの,だいたいのことは,話し尽くしました。
長々と,お付き合い下さり,ありがとうございました。
ベンさん
こんにちは、渾身です。
週末に向けて立て込んでおりまして、アメブロの方の問い合わせの件も含めて後日お返事させてください。
勉強になる内容、ありがとうございました!
こんにちは,渾身さん。
海外のサイトを回って,ネット・ネット株について調べてみました。
私の邦訳で申し訳ないのですが,
http://www.aaii.com/computerized-investing/article/benjamin-graham-s-net-current-asset-value-approach.pdf
(pdf ファイルなので,注意して下さい。)
正味流動資産価値 (NCAV: Net Current Assets Value)
> NCAV = current assets – [total liabilities + preferred stock]
正味流動資産価値 = 流動資産 – [負債総額 + 優先株]
解散価値( = 清算価値) ≒ 正味流動資産価値 なので,
解散価値 ≒ 流動資産 – 負債総額
で間違いなさそうですね。
http://www.gurufocus.com/grahamncav.php
> Net Current Asset Value ( NCAV) = Current Assets – total liabilities
正味流動資産価値 = 流動資産 – 負債総額
> Net Cash = Cash and short-term investments – total liabilities
正味現金 = 現金と短期投資 – 負債総額
> Net-Net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (0.75 * accounts receivable) + (0.5 * inventory) – total liabilities
ネット・ネット運転資本(NNWC) = 現金と短期投資 + 売掛金勘定*0.75 + 棚卸資産*0.5 – 負債総額
ちょっと,長文すぎなので,分割します。
ここで,一般的な,
正味流動資産(Net Current Assets) = 運転資本(Working Capital) = 流動資産 – 流動負債
の定義が問題になりますが,
http://deepvalueinvestor.com/net-net-working-capital/
> 1) Net Working Capital = Current Assets – Current Liabilities
正味運転資本 = 流動資産 – 流動負債
> 2) Graham’s Net Working Capital = Current Assets – Total Liabilities
グレアムの正味運転資本 = 流動資産 – 負債総額
とあります。
おそらくグレアムの正味流動資産の定義も,一般的なものとは違うのでしょうね。
あるいは,解散価値を考える時だけ定義を変え,その他の場合は一般的なものを使うという,二重の基準(ダブル・スタンダード)をとっているのかもしれません。
そして,正味流動資産価値(NCAV)アプローチと,ネット・ネット運転資本(NNWC)アプローチは,違うということになるのでしょう。NNWC は,NCAV の発展型というか,そんな感じなんでしょうね。
ネット・ネットでは,
ネット・ネット運転資本を算出し,それと時価総額とを比較します。価値に対する価格の安全余裕度として,前者が後者の1.5倍以上の銘柄を選択することになるのでしょう。
またまた,長文で,ごめんなさい。そして,ありがとうございました。すっきりしました。
ベンさん
返信遅れてすいません。
こちらもすっきりしました!
バリュー系はどうしても長期投資向けなので、そのままではリターンも小さく、分析するモチベーションがあまり沸かなかったのです。
が、ベンさんのおかげで四季報を読み込むのが少し面白くなってきました。
直接の投資戦略と言うよりも、ユニバースを選定するのに利用できるかもしれません。
たとえば、割安の度合いとイベントへの反応、テクニカルの効きなどを調べると面白そうです。
下記、アメブロでのご質問の回答です。
2013年秋号のデータ。
バリュー度=(流動資産-流動負債-固定負債-時価総額)÷時価総額
として上位を買い、下位をを売る戦略でした。
ユニバースは電気機器セクター。
バリュー度順位
1位:船井電機
2位:ホシデン
3位:双葉電子工業
4位:ミツミ電機
5位:池上通信機
6位:日本電子材料
7位:ナカヨ通信機
8位:双信電機
9位:エスペック
10位:古野電気
(ちなみに最下位(超割高)はソニー)
傾向としては、やはりバリュー度の高い銘柄は直近赤字決算が多いですね。
つまり、グロース度が低いので相対的にバリュー度が高くなっているという。
したがって、バリュー投資でもその事業の将来の収益性を分析する必要があるのかなと。
資産があっても、それを食いつぶすだけの企業であれば、当然厳しい評価(低い株価)を突きつけられるのでしょう。
とはいえ、逆に何かポジティブなイベントがあれば、安全域が大きいだけに敏感に反応する銘柄なのかもしれないので、そういう面白さはありそうですね。
ちなみに、東証のスタイルインデックスにおけるパフォーマンスは、Smallバリューが最もよいようです。
http://www.tse.or.jp/market/topix/lineup_data/f_4_style.pdf
こんばんは。
教えていただいて,ありがとうございます。
渾身さんのトライも,NCAV アプローチとして捉えることができるかもしれません。
ただ,古典的バリュー投資の要諦は,市場のアノマリーをつくことだと思うんです。
異常値のような,普通あり得ない株価の割安株は,いつか価値の見直しがあるという。
おそらくは,渾身さんの思想とは異なるアプローチからの投資法であることを前提に,聞いて下さい。
1位:船井電機
正味流動資産 91,677(百万円)
時価総額 36,059(百万円)
安全余裕度 154%
(注)安全余裕度 = 正味流動資産 / 時価総額 – 1 50%以上が,割安株
10位:古野電気
正味流動資産 54,856(百万円)
時価総額 20,253(百万円)
安全余裕度 -17%
去年の9月頃は,四季報CD-ROM を買ってなかったので,今年の夏号のデータに基づいて計算しました。
なので,時価総額は不正確ですが,一番安いものを使いました。
また,希薄化要因等の調整も行なっていません。
上の計算のとおり,10位:古野電気の時点で,正味流動資産(割安)株からは,漏れています。
これは,ある意味当然で,154銘柄のうち,正味流動資産(割安)株が10銘柄も見つかれば,アノマリーでもなんでもないですから。
今日は,ここまでにしたいと思います。
長文,お読み下さり,ありがとうございました。
おはようございます。
のっけから,訂正です。間違いがあります。
10位:古野電気ですが,
> 正味流動資産 54,856(百万円)
を
正味流動資産 16,882(百万円)
と直して下さい。
結局,昨年の9月17時点での,正味流動資産(割安)株は,電気機器セクター154銘柄のうち,2位のホシデンまでの2銘柄までということになります。
残りの152銘柄は,アノマリーと見なしません。実は,0かもしれないと思っていましたから,予想を超える大健闘です。
また,期間は,2か月は少な過ぎると思います。賢明なる投資家の15章「積極的投資家の株式銘柄選択」のある一節「正味流動資産価値以上の割安銘柄」では,
「ただし、…買ってすぐに値が上がらなくても我慢できる忍耐力があれば、…。前の版では、執筆当時(一九六四年)に行った…。その投資対象は、正味流動資産価値三〇、帳簿価格およそ五〇に対して、二〇で売られていた…利益はすぐに出ないことは分かっていた。だが、一九六七年八月、…五八・七五…」
とあり,3年間半で165%のリターンを挙げた例が紹介されているぐらいですから。
> 資産があっても、それを食いつぶすだけの企業であれば、当然厳しい評価(低い株価)を突きつけられるのでしょう。
そのとおりだと思います。一方、「企業の成果も株価のパフォーマンスもともに長期的、一般的には平均に復帰する」(バリュー投資入門から)ことを念頭に入れた投資も、ありなのかなと思います。
長くなりましたので,また時間を置いてポストしますね。長文,お読み下さり,ありがとうございました。
ベンさん
詳細な分析ありがとうございます!
>また,期間は,2か月は少な過ぎると思います。
トレード期間の問題は、トレードスタイルの問題になるので、そもそもの前提が異なるため議論しづらい部分ですね。
自分の場合、毎月5%のリターンを目標においており、毎月利益を出しにいっています。
それと、3年半我慢する忍耐がないのと、データサイエンティストという職業上、多数の期待値優位なエッジにベットして収益の安定を図るスタイルが性に合っているので。
いつか、ありあまる資産を持ち、企業を応援するという気持ちになれば別ですが。
なので、グレアムの考え方でも自分のトレードスタイル、時間軸に引き込めないかと考えて検証しました。
こんにちは。
> トレード期間の問題は、トレードスタイルの問題になるので、そもそもの前提が異なるため議論しづらい部分ですね。
はい,そうだと思いました。バリュー投資は,1年以上の中・長期投資が前提ですから。
特に,資産のバリューだけに着目した投資は,時間がかかります。
(ちなみに,NNWC を使って,対象を全社にして2年間ぐらいの期間で試したら,市場平均を超えると思います。)
逆説的に言えば,だからこそ,この投資法は,90年弱たっても,使えるんでしょうけど。
> とはいえ、逆に何かポジティブなイベントがあれば、安全域が大きいだけに敏感に反応する銘柄なのかもしれないので、そういう面白さはありそうですね。
この場合「何かポジティブなイベント」の「何か」の部分が問題ですね。
ターンアラウンド,黒転,経営者の交替,買収,訴訟の終了ぐらいでしょうか。
この中で,使えそうなものがあれば,いいですね。
順序が逆になりましたが、
> したがって、バリュー投資でもその事業の将来の収益性を分析する必要があるのかなと。
資産のバリューだけではなくて,資産のバリュー+収益のバリューを使うのが,実際には多いと思います。
DCF法がこれに当たるのではないかと。
この場合,資産のバリューは,解散価値ではなく,再調達価額になると思います。
また,キャップレートも使われますね。
このエントリーでは,これぐらいでしょうか。お付き合い,ありがとうございました。
ベンさん
こちらこそ勉強になりました!
どこかでバリュー株をからめた検証結果を公表するかもしれませんが、そのときはまたご意見ください。